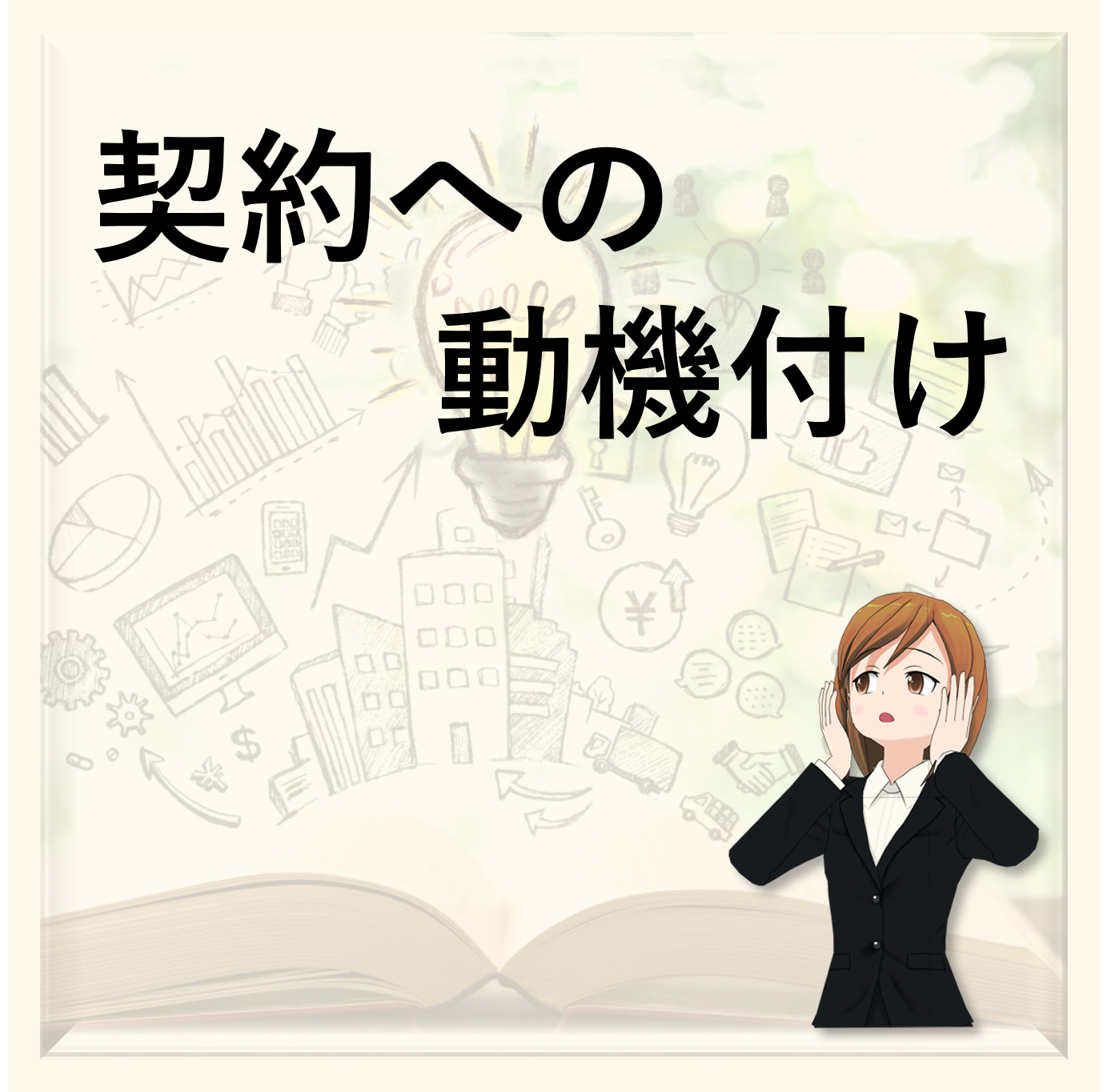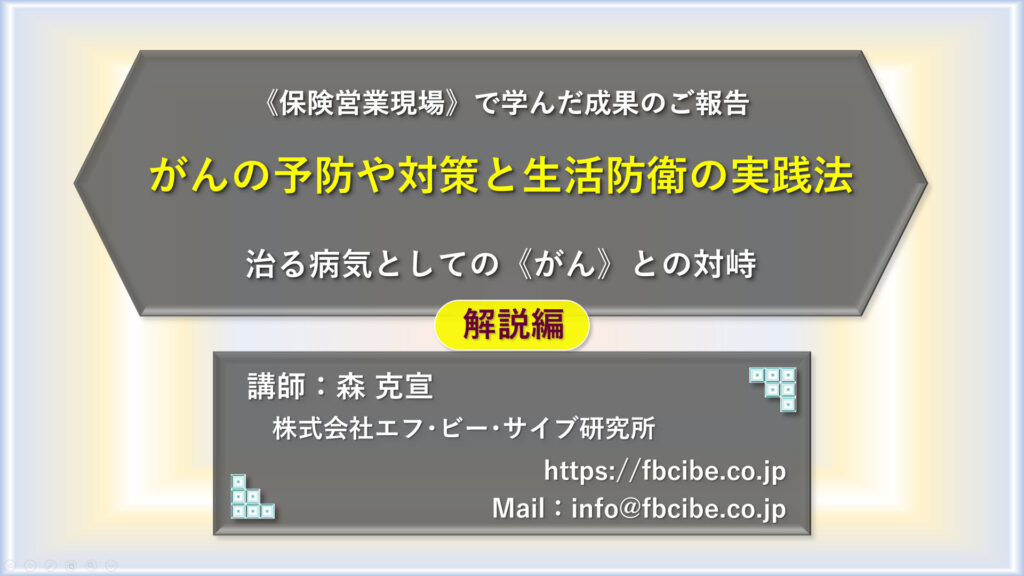良い習慣は、それに繋がる《好ましい活動》を通じて《良い結果》をもたらすことが多いでしょう。その一方で悪い習慣は、必要な活動に繋がらない分、《残念な結果》を生みやすいかも知れません。そして、そんな《傾向》の下で、保険の顧客層も大きな影響を受けてしまっているかも知れないのです。少し《検証》してみましょう。
(執筆:森 克宣 株式会社エフ・ビー・サイブ研究所)
1.自他の《本音》を探す時の困った傾向
最近のYouTubeでよく見かける、『誰それが本音を語った』というタイトルの動画内容は、私たちには意外に思える時があるかも知れません。たとえば『アメリカ大リーガーの大谷選手の活躍に、チームメートが《本音》を語った』というタイトルがついた動画で、チームメートが大谷選手を絶賛していたりするからです。
そんなケースでは恐らく、英語の《True Feeling:トゥルー フィーリング》を《本音》と直訳しているのでしょう。もちろん日本語の《本音》にも《嘘偽りのない真の感情》という意味がありますが、私たちには、むしろ《建前》に対応したニュアンスで《本音》を使う習慣の方が強そうなのです。
2.建前に対する《本音》が持つイメージ
その際の《建前》には、他者に聞かれても困らないもの(他者に聞かせたいもの)である一方で、《本音》には心の中に隠しておきたいものというイメージがあります。そのため《本音は心に隠している悪い思い》として捉えられるケースが少なくありません。悪い思いでなければ隠す必要は少ないからです。
たとえば、『彼は建前では家族ファースト等と言っているが、本音では家族を《自分の社会的成功》にとって足手まといだと思っている』という風に、《本音》という言葉を使いがちだということです。
3.本音を尊重する方向に傾く現代の文化
ところが昨今では以前とは違って、YouTube上に限らず《建前=社会性》を《本音=個人的な感情や損得》よりも優先する傾向は弱くなって来ています。そのため『自分の本音はともかくとして、家族のために生命保険を契約しよう』と考えるより、『本音が生命保険契約を否定しているなら、それを建前で隠す必要はない』という感じ方が、こう言ってよければ、自然に聞こえてしまう傾向も出ているということです。
それはそれで仕方がない社会感覚傾向でしょうが、保険営業者の皆様まで《そんな気分》になってしまうとしたら、問題がないとは言えません。
4.それが何故保険営業上の問題なのか?
なぜ《問題》になるかと申しますと、顧客の《本音》を気にし過ぎるあまり、『生命保険を契約しても損にならない』『こんな得がある』という《本音を満足させようとする》スタンスに立ちがちになるからです。かつて、節税効果を過度にアピールしたのも、顧客、特に経営者の本音を恐れたからかも知れません。
しかし、よくよく考えてみれば、『たとえ自分の損になっても家族や従業員のためになれば良いではないか』と言い切ったとしても、少しも不都合ではないはずなのです。現に、仕事で疲れ切っている休日でも、家族が喜ぶからと言って、レジャーに出掛けるパパやママも少ないとは言えないでしょう。
5.家族のために行動する《パパやママ》
さて、そんなパパやママを、本音では《休みたい》と思っているからという理由で責められるでしょうか。実際《心が清くない》《本音を浄化せよ》という見解もあり得るでしょうが、いくら何でも責めるのは不適切でしょう。
そのパパやママは、心の中にどんな《思い》があれ、レジャーに家族を連れて行くという《行為》をしているからです。しかもその《行為》にも、ちゃんとした思いや背景があるはずです。
もし《休みたい》という《思い》が本音だとするなら、家族を喜ばせたいという《思い》も本音に数えるべきでしょう。しかも実際に《行為》を伴う分、《より強い本音》とも言えるはずなのです。
6.金融機能としての生命保険の存在価値
《損をしたくない》という感情的本音は、私たちを《損をしない行為》に走らせますが、《他者の役に立ちたい》という意志的な本音は《役立つ行為》の動機になります。
つまり、本音はしばしば、《利己感情》と《行為意志》の両方にまたがり、それぞれがそれぞれに似合った《行為》を呼び起こそうとしているということです。一見すれば《悪と善》の戦いのようでもあります。
7.行為に至る動機に働き掛ける営業姿勢
そう捉えると、生命保険営業にも《利己感情》に向けて《損得》を語るばかりではなく、他者を思う《行為》に至る《動機》に強く働き掛ける話法が必要なのではないかとも思えて来るのです。
もちろん《損得》を語ってはいけないと申し上げているのではありません。ただ、損得に傾き過ぎると、投資や貯蓄等との比較の上で、生命保険の《資金形成力》から見た存在価値が薄れがちになると指摘したいわけです。
生命保険の、単なる《損得》では語り尽くせない《機能》を軽視すべきではないのです。ただ、その際の《語り方》は、損得の指摘よりもはるかに難しくなるでしょう。
8.正面からよりも効く遠回しのトーク法
そんな事情から、新日本保険新聞(生保版)で、2025年4月から第4週の第3面《全面企画記事》として、行動意欲を駆り立てるための《第三者話法》の紹介を、翌年3月までのシリーズとして連載させていただくこととしました。
同生保版のシリーズ記事は、新日本保険新聞社のご厚意にもより、1997年4月に始めて以来、今年度で29年目を迎えます。その間、生命保険市場でも様々な出来事がありましたが、昨今では、単に提案型や情報発信型でのスタンスでの取り組みに留まらず、《ユーザーの心の中》にまで、もう一歩踏み込まなければ、生命保険の存在価値が見失われてしまうという危機感を抱くようになりました。
9.新日本保険新聞の年度シリーズの中で
上記の話法の有用性とイメージは、2025年6月23日(第4月曜日)付けの新日本保険新聞(生保版)の第3面に、シリーズ第3話として掲載されます。その第1話は、本サイトでもお読みいただくことができますが、第3話は7月以降に、本サイトでも掲載したいと考えています。
第1話だけでは、『なぜ、良き本音を(契約という)行為に繋ぐために第三者話法が必要になるか』を明示してはいません。しかし、上記7.までの趣旨を《ある保険営業者の方の体験》を通じて取りまとめた第3話では、《思考習慣の変更あるいは革新》が、なぜ今日重要になっているのかを、ご理解いただけるのではないかと考えています。
10.思考習慣と同様に重要になる生活習慣
ただ、保険営業で重要になるのは《思考習慣》だけではありません。たとえば《がん予防セミナー》のように、『生活習慣を見直そう』という指摘も有効になるはずだからです。もちろん《がん予防セミナー》の内容は、《がん予防のための生活習慣改善》と《定期健診の重要性》が中心テーマですが、その底流には、『先々を考えずに《今だけ》を見て生きる習慣を見直そう』という呼びかけがあるからです。
そんな呼びかけをするのは、長期的視点に立たなければ生命保険の価値など見えるはずもないからです。しかも、単に先々のリスクを捉えるだけではなく、生命保険が時間の経過の中で変えて行く機能にも目を向ける時、顧客層にも『自分の感性や生き方に合った保険を選ぶことが重要だ』と思えるはずだからでもあります。