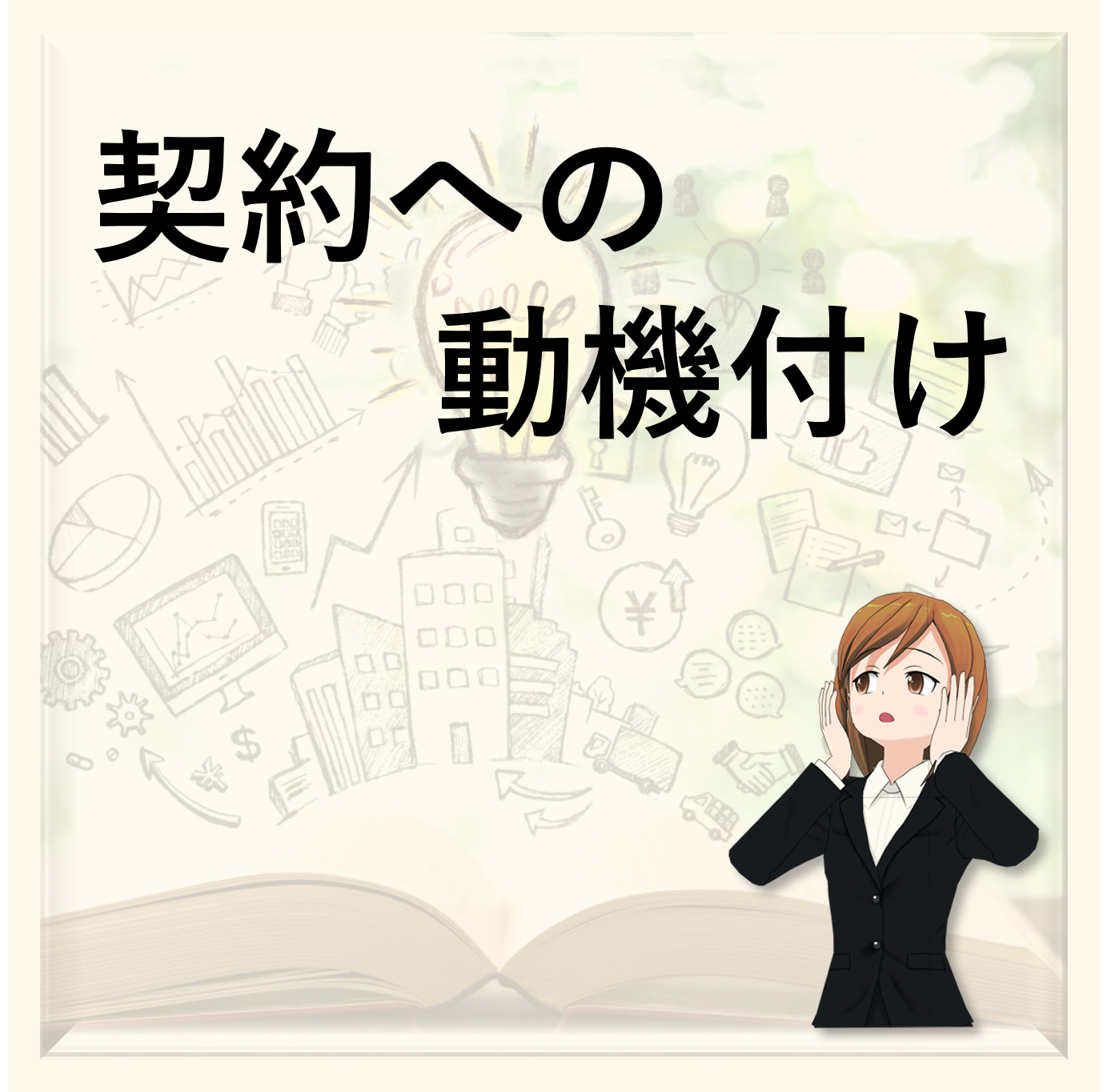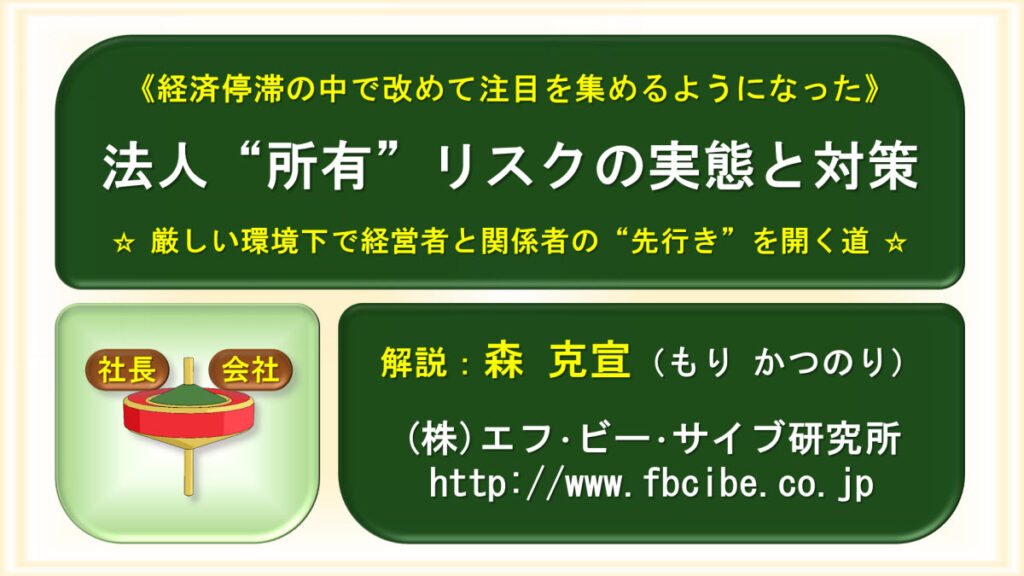人には必ず《死》が訪れます。『人生で唯一確実なものは死である』と言う人もいるくらいです。しかし、それ程確実なものが《リスク》とされるのは、その《死》が《いつやって来るか分からない》からでしょう。つまり《生じるタイミングにリスク性がある》ということです。
では、そんな《人の死》も含めた《法人の必然リスク》には、どのようなケースがあるのでしょうか。
(執筆:森 克宣 株式会社エフ・ビー・サイブ研究所)
1.法人自体の《死》はかなり錯綜的?
今更申し上げるまでもないかも知れませんが、法人にとっての《死=終焉》はかなり錯綜していると言えそうです。なぜなら、①法人自体の終焉(倒産や廃業)以外に、②現経営者の死や③後継経営者の死による事業終焉の危険性発生に、④自社株所有の行方が絡むからです。《絡む》と申しますのは、①~③には、常に④の要素が同時発生するということです。
しかも、そこに⑤贈与税や相続税納税まで加わると、事態は更に重くなり得ます。
2.企業が元気なままでの経営者の他界
会社の事業が継続されている中で、自社株を100%保有する経営者が他界(上記②)したとしても、それが必ずしも企業の終焉に直結するわけではありません。たとえ後継経営者が決まっていなくても、事業は過去からの経緯の中で、少なくとも一定期間は継続可能だからです。その結果、自社株は《法定相続人が相続》することになります。
相続が発生すれば、一定条件の範囲内で相続税が発生します。しかも、自社株の相続税評価額は《相続発生の日》すなわち、経営者の《他界日》で算定されることになります。
3.経営者の相続人の最大リスクとは?
たとえ、その先経営者の急死によって事業が終焉することが高い確率で予想されても、そして事業の内容を一切知らなくても、相続人は相続税を支払わなければなりません。相続発生日の翌日から10ヵ月以内の支払いが原則です。
相続人が事業に関与していないとしたら、相続人は《ほとんど無価値》な財産(自社株)を、相続税納税の上で取得することにもなりかねないわけです。もちろん、相続人は相続放棄をすることができますが、その際には経営者の自宅等を含む《個人財産の相続》をも放棄しなければなりません。この事態は相続人の《大きなリスク》、もしかしたら《最大のリスク》になるかも知れません。
そのため、②-1)相続税納税対策のみならず、②-2)相続争い(相続人間の自社株の押し付け合い)対策は必須なのです。
4.経営者より先に法人が終焉する場合
では、100%自社株を所有する経営者の死より先に法人経営が行き詰まる場合(上記①)はどうでしょう。
会社倒産によって発生する債務は、経営者自身が会社の借金の保証人でない限り、法人が、その財産の範囲内で負うのが原則です。ただ、経営者は特別の債務を負わない場合でも、その後の収入源を失うことになります。それは従業員も同様ですから、経営者には《従業員に対する何らかの補償が求められる》ケースが多いでしょう。
少なくとも、売掛金等の回収が難しくなる中で、買掛金や借入金を返済しながら、給与や退職一時金等を支払うとしたら、経営者の個人財産は無傷では済まされないケースの方が多くなり得ます。
経営者が会社の債務保証をしている場合、経営者の個人財産はもっと大きな負担を背負い込むことになります。法人が《倒産・廃業リスク対応のための資金源を通常の事業運営とは別に持つ》ことは重要なのです。それは債権者や従業員のためのみならず、収入源を失うことになる経営者のためでもあるからです。
5.意外に軽視される後継経営者の急死
ただ、案外軽視されがちなのが《後継経営者の他界》(上記③)でしょう。後継経営者が亡くなっても、現経営者がしっかりしていれば事業は存続されるというのは、そう言って良ければ《理屈》に過ぎません。後継経営者を失った企業は同時に、《先行きの事業継続への信用》を失うのが現実だからです。
その信用喪失は、金融機関や取引先のみならず、社内にも広がって行くでしょう。社内の人員が離散すれば、事業は容易に危機に陥ります。もちろん、その際、社内のキーパーソンが経営権を承継することができますが、自社株を承継するためには、相続人以上の贈与税や相続税負担が必要になります。
6.後継者を被保険者とする企業保険?
後継経営者を失った現経営者は、《生涯現役経営者》の仲間入りをし、その後上記2.でご指摘した問題に直面してしまいます。しかも、後継経営者の存在で《安心》していた分、元来の生涯現役経営者よりも準備不足に陥っている可能性が高いのです。
後継経営者を被保険者とした企業保険は、決して《検討対象外》にはできないでしょう。もちろんその際、終身保険等にしておけば、リスク対策以外に、適切な時期に解約して《将来の投資資金》に回したり、《後継者自身の退職金の準備資金》等に充てたりすることも可能になります。
後継経営者が《しっかり》しているケースでは、現経営者の引退資金に備える保険にするのも一案でしょう。
7.他の選択肢との組み合わせを考える
上記のような諸問題の対策には、企業保険や経営者個人の保険契約が役立つはずです。その際、単に保険契約をするのではなく、《死亡保険金や解約返戻金の使い方》に対するプランが必要になるのは、申し上げるまでもありません。しかもそれは、上記1.の①~⑤の全てを視野に入れたプランでなければなりません。
しかし①~⑤の対策全てを生命保険に委ねるのでは《重過ぎる》、つまり《保険料負担が大きくなり過ぎる》ケースが多くなるでしょう。負担が大きいと、保険の魅力は大きく後退してしまいます。
そのため、生命保険の提案に際しては、《他の方法》との組み合わせで保険契約者の負担を軽減する方法を考えることが重要になるのです。
8.2026年4月以降も続く事業承継税制
他の方法とは、たとえば《事業承継税制》の推奨です。事業承継税制の《特例措置》は、2026年3月末の特例承継計画の提出期限を過ぎれば使えませんが、その後でも《一般措置》は活用可能です。この制度は、自社株に係る贈与税や相続税の全部又は一部の支払いを、一定の要件を満たすことを条件に繰り延べするもので、相続人のみならず相続人以外(親族外も可)を事業承継者に立てる場合にも適用できます。
自社株を承継する後継者には、猶予された税金を支払うために準備する《期間》ができるということです。その準備のために終身保険を契約しておけば、想定外の死亡時でも、後継者の相続人の負担は軽減できます。
9.その他の対策をも視野に入れるべき
その他にも、企業を丸ごと売却(M&A)したり、事業や資産の一部を売って再建や終焉の《資金》を作る方法もあります。M&Aに関しては、それを支援する専門機関がありますし、設備や不動産の売却にも、それぞれの地域に《業者》が存在するでしょう。ネット検索で見つけた上で、具体的な支援内容を確認しながら業者を選定することが可能なはずです。
ただし、保険営業者の皆様が、以上のようなサポートや業務代行を行うのは非現実的だと言えます。そのため、経営者との《特別な対話関係》を形成することが有用になるのです。
10.経営者との《特別な対話関係》とは
その《特別な対話関係》とは、保険営業の皆様が《会社のマネジメント》自体について語り合える存在になることです。もちろん、事業推進法や利益拡大法を直接話し合うのではありません。あくまで《保険》に限らず《保険を超えた》話題、たとえば《他社の課題やその克服の事例》や《保険を一選択肢にするかのようなリスク対策のアイデアを語り合う相手》として、経営者に認識されることなのです。
保険営業者の皆様は、既に代理店の経営者かも知れません。そうでなくとも、多くの経営者との対話の中で、マネジメント上の問題やリスク対策例を《多様に見聞》できるポジションにあります。そんなポジションを経営者に《感じさせる》ことが、今後の《企業保険提案》にとって、ますます重要になって来るということです。
保険だけでリスク対策をするには限界がありますが、どんなリスク対策にも《資金》が必要ですから、そこに様々な形で保険提案を組み込む余地が生まれるからです。