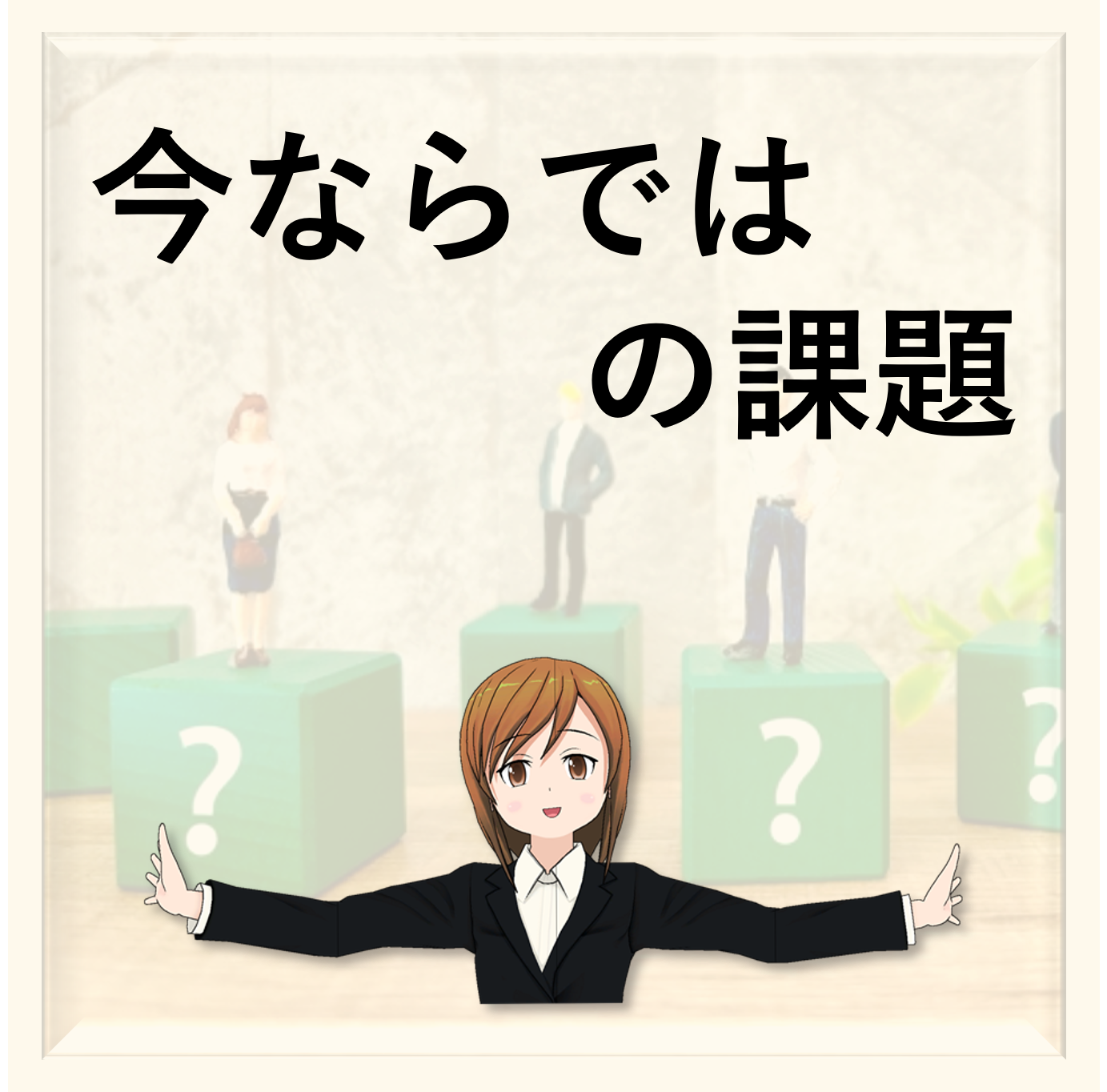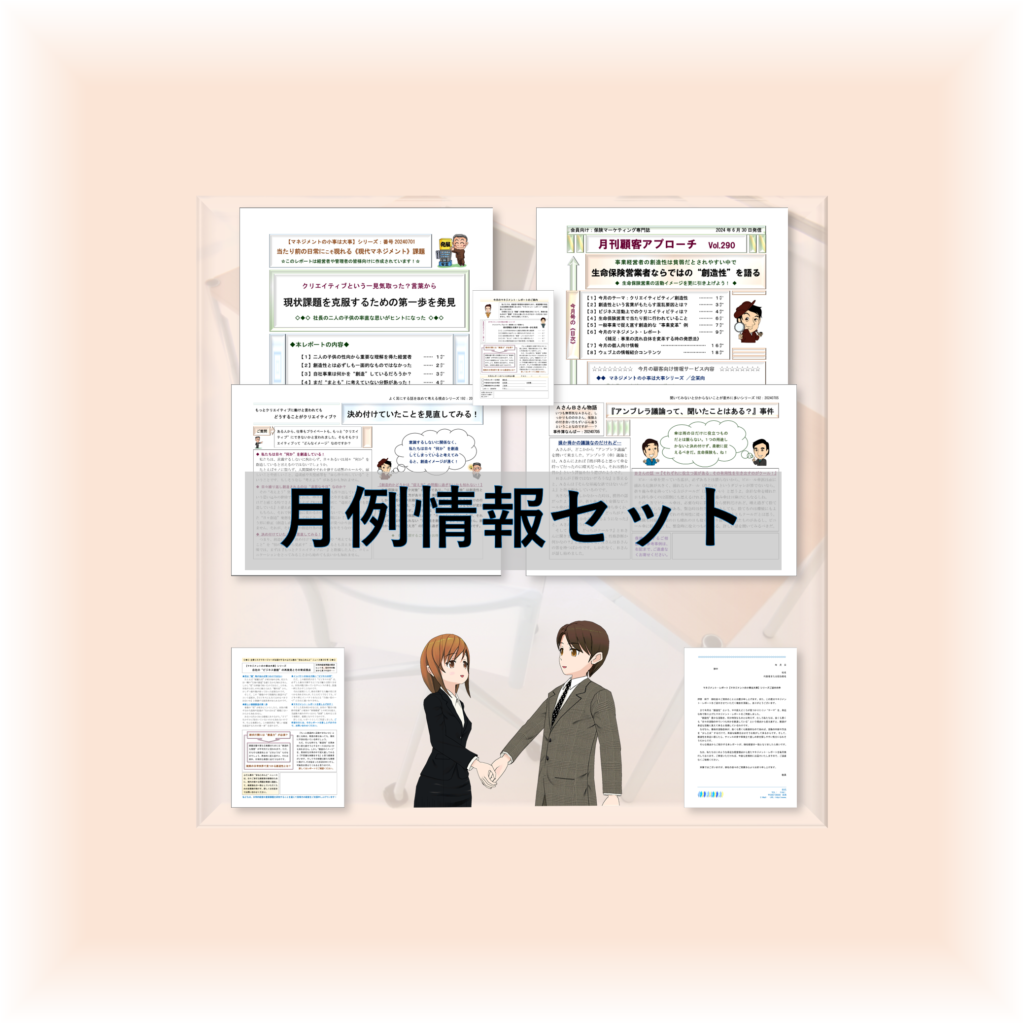うんざりするほど《迷惑メール》が増えた今日、顧客アプローチの在り方も、大きく変容して来ていると言えます。ただ、それは《どのような》変容なのでしょうか。そして今、《どんな構え》が求められるのでしょう。まずは、他の業界の《例》から見て行くことに致しましょう。
(執筆:森 克宣 株式会社エフ・ビー・サイブ研究所)
1.ある住宅メーカーでの出来事がヒント?
会社の規模は中堅でも、地域内での《住宅販売件数》では定評がある住宅メーカーに、Aさんという設計担当者がいました。Aさんは『設計者の技能は、顧客の声で成長する』という信念を持っていたそうです。そのため、同社が実施する新築住宅の2年点検や5年点検に際してAさんは、修繕担当者に同行し、『顧客の生の声』を聞いていたのです。
顧客の生の声には、机上では到底学べない《生きた不満や喜び》を感じさせられます。そして、そこで得た見識が《次の新築設計》の際に、顧客との《やり取り》の中に生かされるのです。
2.社内の営業研修の講師まで務めた設計者
そうした活動にいそしんでいた頃、Aさんはしばしば『営業の会議や研修にも(講師として)呼ばれた』そうなのです。どんな切り口で提案すれば選択に迷う顧客のハートを掴めるかを教えて欲しいという《社内の依頼》が、営業現場や経営陣からもたらされたからです。
同社の営業担当者は、新規開拓に忙しく、既存先を回る《習慣》を持ててはいなかったようです。営業責任者が、既存先への訪問を勧めても、営業担当者は《顧客のクレーム》が怖くて、腰が引けていたと言います。
3.顧客数が増えるにつれ活動は困難化
しかし、販売件数が増えるにつれ、Aさんの設計業務も多忙になり、既存先訪問が難しくなって行きます。Aさんは『このままでは顧客満足度を上げる見識を、これ以上深められない』と悲観し始めました。特に『顧客の在宅勤務が増えたコロナ禍の時期に、顧客の声を聴けなくて、設計に自信が持てなかったことがある』とも言われるのです。
ただ、Aさんは沈黙してはいませんでした。営業担当者に了解を取ってもらい、既存先に《設計者の立場からのメルマガ》を送ることにしたのです。しかも、その文面の末尾には《返信大歓迎》という一言が記載されていました。
4.顧客の声はそれだけでも《生きた教材》
返信はそれほど多くはなかったようですが、『返信者の話には濃く深いものが多かった』そうで、その後のメール交換や電話連絡の中で、《在宅勤務》上の設計の不満点が、急速に明らかになって行きます。
在宅勤務自体は『ある種のブームが去った』ようですが、その時の《情報交換》で得た見識には『《目からうろこ》の内容が少なくなかった』とまで、Aさんは言います。『住宅には住んでみなければ分からないことが多い』のです。
そしてAさんは、今では『新規先探しばかりではなく、既存先と《情報交流》に励もう。そうすれば、紹介が増えるだけではなく、営業話法がパワーアップする』と、営業部門を鼓舞しているのだそうです。
5.一つの事件から活動は一時停止したが…
Aさんの《鼓舞》は、情報交流を始めた若手営業担当者が、顧客からのクレームを受けて《心を病んだ》ことで、組織活動としてはペンディングになっています。しかしAさんは今も、『顧客を満足させる力や新たな開拓力を身に付けるには、既存先との交流こそが大事だ』という考え方から、メールマガジンを続けていると聞きました。
一方で、生命保険の営業者で、《気付きリードマーケティング》の会の会員の方々も、同じように《月例情報》を既契約先や見込み先、あるいは解約先に発信しておられます。解約先からの再契約の話は聞きませんが、既契約先からの保険に関する相談や顧客の紹介は、ぼつぼつあるようです。《繋がり》は、非常に重要なのです。
6.驚くような《保険の話》を顧客から入手
しかも終身保険の契約者から、《月例情報》のお礼とともに『面白い話を聞いた』というケースもあるようです。情報発信を続ける保険営業者のBさんに対し、ある既契約者が『終身保険て不思議だね』と言うのです。契約後、数年が過ぎると『月払い保険料よりも、その月のキャッシュバリューの増加の方が大きくなる』からなのだそうです。
キャッシュバリューの増加は、支払済み保険料の全体の成果ですから、支払い済み保険料額が増えるにつれ、月払い保険料よりも大きくなるのは当然ですが、その既契約者は『それは分かっているけれど、月ベースでは、支払っている額よりもキャッシュバリューの増額の方が大きくなるのは、単純に喜ばしい』と言うのです。そして『解約すれば、この増加効果もなくなるんだよね』とも言います。
7.机上計算と現実的満足感は同じではない
理屈の上では、終身保険を解約して、そこで得た資金を《高効率》の投資に変えた方が、確かにメリットはあります。しかも、契約して一定期間経過後も、解約返戻金(キャッシュバリュー)は、支払済み保険料合計額の水準には、なかなか至りません。ところが、その既契約者は『保険料が掛け捨てになるケースと比べたら、その差は気にならないよね』とも言うのです。
この《大らかな既契約者》の話は、Bさんに『死亡保障がありながらも、保険料が運用される』という仕組みの《新しい解釈》をもたらしたようです。保険料支払いの全期間を対象する《机上計算》では、到底気付けないものです。
8.生命保険の商品性は住宅とは大きく違う
そんな保険営業者のBさんは、住宅設計者のAさんの話に共感されます。特に、既契約者との交流が、たとえクレームを受けても《新たな勉強の重要な材料になる》という点に共感を示すのです。
そして『年月とともに劣化して行く住宅とは異なり、生命保険分野では、情報発信の継続はクレームの素になると言うより、良好な関係形成の基盤になるケースの方が多い』とも指摘されるのです。
9.生命保険検討の先生も生徒も共に顧客?
情報発信は、今や確かに、新規先の開拓や、見込み先のクロージング促進のためだけではなく、既契約先との実りの多い交流をもたらしてくれるものとして位置付けるべきものになったかも知れません。かつてのように《見込み先》がどんどん見つかる環境にはないため、一見《細く見えるパイプ》でも、そこに新たな顧客との接点や共感点を増やすヒントがあるなら、軽視する理由がないからです。
Bさんは、『既契約者は、生命保険導入の先生で、新規先や見込み先がその生徒だ』と考えると、状況の変化と共に刻一刻変わり得る《生命保険の満足ポイント》が、非常に見つかりやすくなると言われます。
それは、今ならではの情報発信活動の1つの重要な成果なのかも知れません。