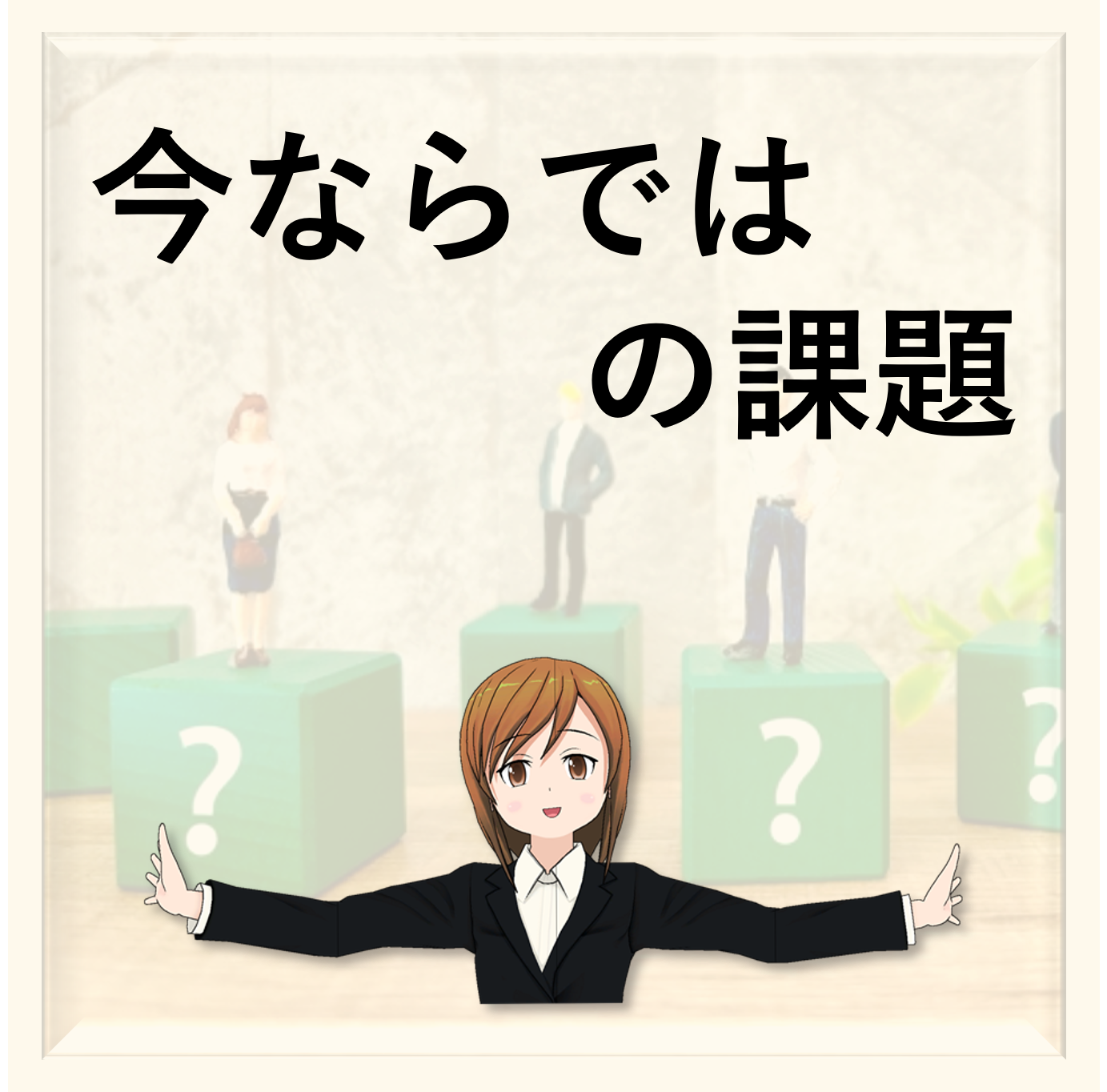代理店の従業員や保険会社内の部下、あるいは紹介や営業活動のパートナーが《期待通りに動いてくれない》ケースは少なくないかも知れません。そんな時『やはり教育や指導が必要』と痛感するのですが、そもそも《人》の教育や指導は《どのように》行えば、効果が生まれやすいものなのでしょうか。
(執筆:森 克宣 株式会社エフ・ビー・サイブ研究所)
1.一昔前なら《真似》が最大の教育指導だった
少し前までなら、《営業活動の指導》と言えば、ベテランがお手本を示して、後輩がそれを真似る形が多かったと思います。もっと前には、『営業法は(ベテランをお手本にして)盗め』とか『ベテランの背中を見て学べ』等と言われたものです。
しかし今や、そうした《良き伝統》がうまく機能しなくなってきています。しかも、従業員や部下ばかりではなく、紹介拠点となるべき人の《協力促進》や、営業パートナーの育成についても、同様の悩みが出るケースが少なくありません。期待通りに動いてはくれないということです。
2.その理由を考える前に現代的な視点をイメージ
『なぜ良き伝統が機能しなくなったか』という理由は、段階的に後述するとして、先に《現代的な指導法の在り方》を具体的な例でイメージしてみたいと思います。
たとえば、従業員や部下が『見込み先と親しくはなれるのに、保険の話を切り出せない』とします。その時の《現代的な指導ポイントのベース》には、最低限で《2つの姿勢》が求められるのです。その1つは《①よくやったと言える部分を探すこと》であり、もう1つは《②従業員や部下に、自ら可能性を見つけ出させること》です。
3.はたして《よくやった》部分などがあり得るか
ただ、見知らぬ先と《親しく》なって見込み先を作ったのに、保険の話を切り出せない人に、『よくやった』と言える部分があるのでしょうか。その点については、保険契約に至る道程を客観的に見通すなら、対話ができる程に《名前と顔を覚えてもらって、連絡先を交換した》とすれば、そこまでは『よくやった』と認めてあげましょう。
現代に活動する従業員や部下には、『親しくなったのに先に進めない』という悲嘆にくれる前に、『私は、見知らぬ人と対話を始めるという難事を達成した』という《満足感》が必要なのです。
『そんな甘ったるいこと…』が必要になった理由は、申し上げるまでもなく、《現代社会》は生命保険営業に限らず、先行きに希望が持ちにくくなった社会だからに他なりません。
4.ここまでやったのに《もったいない》と思う!
中途半端な成果を褒めると《やる気》を失うのは、希望に満ちた社会環境での話でしょう。《親しくなる技能》さえついたら、私の将来は(今後の自然な能力アップの中で)安泰だと思うなら、確かに《次を切り開く意欲》は減退するかも知れません。
しかし、現代社会では『ここまでやったのだから、これを無駄にするのはもったいない』という思いの方が、《更に進む必然性》に繋がりやすいのです。他の可能性を探すことには、容易に希望が持てないからです。
5.中途半端な成果の具体的な内容共有が重要に!
その際、ただ《褒めっ放し》にするのではなく、《見知らぬ先と仲良くなった事実》を、その従業員や部下に、こう言って良ければ《自慢》させなければなりません。自慢を許された時、誉め言葉が《リップサービス》ではなく、重要な成果の1つなのだと気付くことができるからです。
しかし、《自慢》と同時に《自戒》させることも不可欠です。その自戒とは、『そんなに親しくなったのに、なぜ保険の話が切り出せなかったのか』という核心的な話です。
6.自戒=試してみたかったと感じ得ることを探す
従業員や部下の話を聞いていると、指導者には『こうすれば良かったのではないか』という突破口が見え始めることがあります。しかし、それを伝えることを急がず、その人に『何か、やりようはなかったのかなあ』と問い掛けて、考えさせるのです。
『全くありません』と言われたら、指導者が感じた可能性を話すべきでしょうが、その人に少しでも考える姿勢があれば、指導者と学ぶ人の両者で《やりようの可能性探しという共同作業》を行うことをお勧めします。この際の可能性は、たとえば『ああ、こんな切り出し方なら、保険の話が出来た。試してみても良かったなあ』と感じ得るものです。
これが2つ目の要点である《②可能性=試してみたいこと》の発見なのです。
7.試してみたいという思いこそが次の行動の源泉
先行きに希望を持ちにくい社会では、『こうすればうまく行く』という観点は、疑いとストレスの素で終わってしまい、実際の行動には、なかなか繋がらない危険があります。しかし、成功するかどうかは別として、『まずは試してみて、また考えたい』と思えるなら、行動に繋ぐ際の壁も低くなっているでしょう。
そして《試して》みるうちに、よほど不運な人でない限り、道が開けて来るのではないでしょうか。成果はほとんどの場合《大数の法則》的に出て来るからです。
それでも道が開けない時には、指導者がそれこそ《話を切り出すお手本》を、見込み先の前で《不運な人》に見せることも、試してみるべきだと思います。
8.現代的な教育指導要点の底流にある2大原則
この《①できたことを賞賛(感謝)して内容を共有する》ことと《②できなかったことの中で試してみたいことを一緒に探す》という指導は、現代では必須の要素になっていると言えそうなのです。
その理由は、既に申し上げた《①先行きに希望が持ちにくい》からばかりではなく、そんな中で《②保険の顧客層も疑心暗鬼に陥りやすくなっている》からに他なりません。
だからこそ、《①希望の減少》に《①できたことの賞賛(感謝)》で活動エネルギーを補充し、《②顧客の疑心暗鬼》に対して《②試したいことを考える》という回り道をとる必要が出て来たわけです。
9.教育のみならず《協力》促進にも応用が可能
この《①できたことに注目する》と《②試したいことを共同作業の中で探す》という視点は、困難が拡大する環境では1つの《行動指針》になり得るはずです。それは、まだ希望が残っていた時には《①できないことに挑戦する》と《②成功事例を真似る》ことが《良き学び》だったのと同じレベルの話でしょう。
そして上記①と②は、紹介を引き受けてくれる人の発掘や実際の紹介促進にも役立つ視点になるはずですし、営業パートナーを育成し、営業活動の協力者を増やす際にも応用が効くと思います。